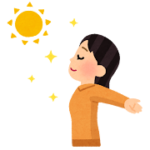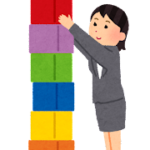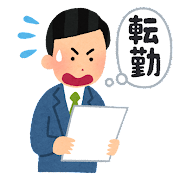
また一人、いなくなりました。
その人と、万物に感謝しているだけで、嫌な人が目の前からいなくなる (‘;’)
ちなみに「いなくなる」とは
- 嫌な人が引っ越す
- 異動したり退職したりする
- 会うこと・かかわる機会が激減する
- その人の嫌な部分が、自分には見えなくなる
- その人が変わり、嫌な人でなくなる
などのことを指します。
ここでは、感謝するだけで嫌な人が目の前からいなくなるメカニズム、感謝する詳しい方法、最近のいくつかの具体例をお伝えします。
感謝すると嫌な人が目の前からいなくなるメカニズム
ここでは、さらっとだけ、お伝えします。
すべての人・モノに周波数がある
すべてのモノは、目に見えない素粒子 (ツブツブ) の集まり。
みんな、元は同じなんだ (^-^)
- 人の体・意識・感情も
- 動物・植物も
- 物質・水・大地なども
- 場所・空間・空気・情報なども
- 現実に起こる出来事も‥‥
この素粒子は、それぞれが「周波数」を持っており、同じ周波数のモノ同士が引き合う性質があります。
たとえば、ポジティブな人にはポジティブな人・場所・出来事などが寄ってきやすくなるし、常に寂しさを感じている人は寂しさを感じるような物・情報・出来事などが寄ってくる可能性が高くなります。
信じられないけど、これは「量子力学」という物理学のお話 ☆
詳しく知りたい方は、ご自身で勉強してみてください。勉強したくなければ、まずは「そういうもの」と思うだけでOK (理系は超苦手なので、私も詳しくはわかりません…) 。
心から感謝をすると、自分の周波数が上がる
周波数には、簡単に言うと「高い・低い」があります。
愛や思いやり、心から感謝をしている周波数などは「すごく高い」。
なので、感謝を習慣にするだけで、自分自身の周波数が上がっていきます ヽ(^o^)丿
(初めは心が伴わない感謝でも、続けるうちに心が伴う期待大!)
周波数の違いで、嫌な人と引き合わなくなる
自分の周波数が今よりも高くなることで、徐々に
- 周りに「いい人」が多くなる
- いい出来事、ツイてる出来事が多くなる
- 物事がスムーズに進むことが増える
などを実感できます (*^▽^*)
気づくと、嫌な人が目の前からいなくなってる、もしくは嫌な人が嫌じゃなくなる (可能性が高くなる)。
なぜなら、自分の周波数が上がることで、相手自体や嫌な出来事と周波数が合わなくなったり、もともと相手の周波数が高くて嫉妬していた場合などは、それを感じにくくなるからです。
私も実感して初めて「納得」できた感じ (飽くまでも「少しずつ」です)!
以下の記事には、私の体験談 (具体例)、周波数の上げ方、注意点などもまとめています。
42歳以降、嫌な人が目の前から消える…。方法&体験談&思うこと | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜 (kinisinai-jibun.com)
どのように感謝すればよいのか
でも「嫌な人に感謝」って難しいし、したくもないよね。
それでも「やってみよう」と思う人だけ、読んでください (;’∀’)
相手の「感謝できる部分」を見つける
まずは、ムリヤリにでも「相手に感謝できる部分」を見つけることです。
- 嫌いだけど、優しいところもある
- 嫌いだけど、あの人のおかげで得することがあった
- 嫌いだけど、細かく指導をしてくれる etc.
「心の奥で、本当は憧れてるから嫌い」というケースもある。
その場合は
- 自分も本当はチヤホヤされたいのかも
- 自分も本当は自由奔放に生きたいのかも
- 自分も本当は穏やかに生きたいのかも
などと「本当の自分に気づかせてくれて感謝」と考える。
どうしても見つからない場合は「反面教師になってくれて感謝」って感じで。
- 「ああいう態度、私は絶対にしない」と決意させてくれた
- 「あの言い方は人を傷つける」と気づかせてくれた
- 「自分は毎日清潔でいよう」と思わせてくれた etc.
全ての人から「学べること」はあるので、その「学べること」を見つけ出せば感謝ができます☆ (でも「どうしても感謝したくない!」と思う人は無理せず‥)
相手に対し「ありがたい」と思う
相手のことは、嫌いなままでOK!
でも、相手のことを「ムカつく」「イヤだな」などと思った後に、
- 心の中で「ありがたい部分もある」と思ったり
- 「でも〇〇のの点では感謝します」と思ったり
- 機械的に、独り言で「ありがとうございます」とつぶやくのもいい。
悔しいので、相手に言わなくてOK (笑) (もちろん、言うべき場面では言った方がいいです)
「いなくなればいいのに」と思いすぎない
初めは、嫌な人が「いなくなってほしい」から、感謝の実践をする人が多いと思います。
でも「いなくなってほしい」より「感謝すること」に集中してほしいのです。
「いなくなってほしい」という思いを忘れるぐらい、感謝できるのが理想!
でも、難しいですよね‥(*ノωノ)
嫌な人が「本当にいなくなるか」に執着しない (とらわれない) 感じかなぁ。「早くいなくなれ!」「まだいるじゃん!」とばかり思うのではなく「実験を楽しもう」ぐらいな感覚でコツコツ続ける。
あとは心地いいこと・目の前の仕事に集中!
嫌な人のことって、つい考えちゃうけど‥。
できれば 嫌な人のことを考えるのは、相手とかかわっている時だけにしたい!
さらっと心の中で感謝したら、相手のことは忘れる。これ、すごく大事なポイント!
「見える所にいる」って場合でも、目に入らない工夫をしよう。
とにかく上手く切り替え、自分の好きなこと・楽しいことをしたり、目の前の仕事や日常生活に「集中」したりできるとよいでしょう (‘ω’)
人・物・出来事に感謝の習慣をつける
「あらゆるモノに感謝!」の習慣もつけられると、どんどん自分の周波数がアップ!
オススメは、一日一回「感謝」の時間を設けること。数分でもOK。
- 湯船に浸かりながら、感謝できることを振り返る
- 今日ありがたいと思えたことを感謝ノートに書く
- 大切な人、ご先祖様、神様などに感謝の言葉をつぶやく
- いま周りに見える物 (電化製品、家具など) に感謝する
- 寝る前に、今日も動いてくれた自分の体に感謝する etc.
以下の記事には「感謝できることを探すヒント」がまとめてあります☆
一人で感謝探しゲームをやってみた。心が乱れた時にオススメ! | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜 (kinisinai-jibun.com)
最近の具体例
「感謝すると、いなくなるかも」の実践。
リアルの世界でも二人に伝え、なんと二人とも成功しました!
中学生の我が子の体験談
我が子が中学一年生の時、
- 理不尽かつ感情的に怒ってばかりの先生と
- 毎日「前髪がダサイ」と言ってくる同級生
のことを「嫌だ」と言ってきたことがありました。
特に先生は多くの人に嫌われており、部活動保護者会で意見する親もいたほどでした。
そこで、人気ユーチューバー・Honamiさんの「決めれば、叶う」という本の該当ページを読んでもらい、感謝する実践を勧めてみました。 (親である私が言うことよりも聞くと思ったので)
勧めたのが、今年の1月中旬。
なんと約2ヶ月後の3月下旬、その先生が他校に異動することが公表されました。
(保護者が意見したこととか、多くの人の「いなくなれ!」という意識が影響した可能性もある。でも、それも含めて「いなくなった」なのです。)
「前髪ダサい」と言ってくる子も、3月ぐらい~なぜか言わなくなり、しかも4月のクラス替えでクラスも別れたそうで、私もびっくりしました ( ゚Д゚)
昔の教え子も成功したっぽい
数年前の9月、特別支援学校で教員をしていた頃の教え子から、連絡がありました。
職場の上司との関係に悩んでいる、という相談。
もちろん悩みに寄り添い、具体的な対処法なども提案した上で、感謝の実践のことも伝えてみました。
この時は「周りの人に感謝をしていると、いいことが起きる可能性が上がる」ぐらいな感じで伝えていたと思います。 (「いなくなるかもよ」的なことは言わなかった)
教え子がどの程度実践したかはわかりませんが、翌年の4月に再び連絡がありました。
「先生! 奇跡が起きた! 上司が別の部署に異動した!」って。
私は、嫌な人自体がほぼいない
こういう実践を含め、いろんな実践をし始めて、早6年。
今は、嫌な人自体が自分の周りに、ほぼ現れません。
- 店員さんや、街ですれ違う人
- 運転中の他のドライバーさん
- 子どもの担任の先生、他の保護者 etc.
私とかかわる時は「みんないい人」って感じ。本当にありがたいです。
コロナ禍の影響もあるけど、愚痴ばかり言う友人知人とは会う機会が激減したし、たまに「感じ悪い」と思う人が現れても、いい意味で「どうでもいいや」と思えるようにもなりました (;^ω^)
まとめ:実験を楽しむ感覚で
「感謝するだけで嫌な人が目の前からいなくなる」のメカニズム、方法、具体例をお伝えしてきました。
奥平亜美衣さんの本を読んでこの実践を始め、私流にアレンジした方法をご紹介したわけですが‥。
初めのうちは、コツコツ続けたら一人また一人と目の前からいなくなり、驚きを隠せなかった!
その後、浅見帆帆子さんやHonamiさんの本でも、同じようなことが書かれていることに気づきました。
感謝の習慣をつけ、人や物事に心から感謝できるようになると、嫌な人が現れにくくなります。反対に不満や愚痴ばかりだと、仮に嫌な人が去っても、また次の嫌な人が現れるものです。
まずは「実験だ~」と楽しみながら取り組む感じで (^-^)
実際に目の前からいなくなれば、やっぱり「心をラクに楽しく」生活できることにもつながります。
その時は素直に喜んでいい。かつ、実践した自分を褒めてあげてくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。