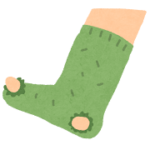このブログは、生きづらかった私が幸せに生きるため、あらゆる実践をしてきた経緯を書いています。
私はおそらく「HSP (超敏感体質)」と「発達障害」の傾向があります。
でも発達障害の方は、おそらく「グレーゾーン」。自己診断をすると、チェック項目に「全く当てはまらない」というものや程度の軽いものもあり‥。HSPと発達障害が複雑にからみ合う~感じ (;’∀’)
ちなみに現在は全く生きづらさを感じず、ラクで楽しいです☆ でも
- 「気にしすぎていたこと」が「超鈍感になった」わけではなく
- 「ネガティブ」→「超ポジティブ」になったのでもなく
- 「ちょっと変な人」→「普通の人」になったわけでもない。
HSPは「気質」、発達障害は「脳の機能」によるからですね。
この記事では、まずグレーゾーンの意味を解説し、一般的に言われる「グレーゾーンの人の対処法」と、「グレーゾーンだからこそ私はこういう実践をしてきました」というお話をします。
グレーゾーンって何?
まず「グレーゾーン」自体の意味ですが、「黒とも白とも言えない灰色のエリア」。すなわち、
【 中間の領域。どっちつかずの範囲。どちらとも決めかねる、あいまいな領域。】
という感じです。「グレーゾーン金利」と呼ばれるものも、ありましたね。
HSPや発達障害などにおいては「その特徴や症状は見られるものの、診断基準を満たさない範囲の人」のこと。
医師や専門家による診断の結果「診断基準は満たしませんが、〇〇の傾向はあります」などと伝えられる場合と、私のように自己診断をした結果「おそらくグレーゾーン」などと言っている場合があります。
ただ覚えておきたいのは「グレーゾーン」と一言で表しても、何から何まで「人それぞれ」ということ。
たとえば発達障害のグレーゾーンの場合、
- アスペルガー症候群の特性だけの人
- ADHDがメインで、他の特性も併せ持つ人
- アスペルガー、ADHD、LD、DCDが複雑に絡み合う人 etc.
本当にそれぞれですし、HSPや強迫性障害、統合失調症など、他の特徴も組み合わさるケースもあります。
他にも、
- 心身の調子が悪い時は、完全に診断基準内に入るレベル
- 特定の症状 (特徴) だけが強く、生活に大きな支障がある
- 本人が多少疲れやすいだけで、生活に支障はない軽いレベル
など、程度の差も実にそれぞれ。
「グレー」と言っても、黒に近い灰色、白に近い灰色、複雑にからみ合うマーブル調、ブロック柄など、いろいろな「グレー」があるイメージですね。
最近グレーゾーンの人が増えていると言われます。
特に、HSPと発達障害には共通項もいくつかあり「もう~よくわからない!」と感じる人もいるかも。
ただ、なんであろうと そこに「苦しさ」や「生きづらさ」があるのかないのかが大切です。
私もそうでしたが「明確な診断がされない」「複雑にいろいろな症状がからみ合う」‥‥「だからこそ苦しい」という人も多いと思います (*´ω`)
発達障害やHSPについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を (チェックリスト付き)!
★私、HSP&発達障害かも【No.2:発達障害を具体例と共に解説】 | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜 (kinisinai-jibun.com)
★私、HSP&発達障害かも【No.1:HSPとは何ぞや】 | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜 (kinisinai-jibun.com)
一般的に言われるグレーゾーンの対処法
医師や専門家による明確な診断がなされれば、治療やカウンセリングに進むケースもあるかもしれません。
しかし「グレーゾーン」の人は、どうすればよいのでしょうか。
本やサイトを参考に「工夫」を取り入れる
本やサイトを参考に、自分に当てはまる特性 (症状) に対する「工夫できる点」を、生活に取り入れていきましょう。
例をいくつかご紹介します。
①HSPにより、目から情報が入りすぎて疲れる人
「『繊細さん』の本 (武田友紀著)」を参考に、
- メガネやコンタクトの度を落とす
- 縁の太いメガネをつけ「ここだけ見ていればよい」と見る範囲を決める
- サングラスや伊達メガネをかける
②発達障害のADHDにより、物を置き忘れたり失くしたりすることが多い人
発達障害やADHD関連の本・サイトを参考に、
- 物の置き場所を決め、使ったら必ずそこへ片付ける習慣をつける
- 自宅の部屋や身の周りなど、整理整頓しておく習慣をつける
- GPSで物の場所を探せるようなキーホルダー型の商品を使う etc.
③HSPや発達障害の自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群により、外部からの刺激に敏感に反応する人
関連する本やサイトを参考に、
- 一人になれる時間や空間を積極的につくる
- 何の予定もない日をつくり、ゆっくり休む
- 作業に集中できる静かなスペースを用意する etc.
特性・症状の軽い方ほど、効果が現れやすいと思います。自分に合った方法を見つけられるとよいですね。
公的機関の支援やカウンセリングを利用する
たとえば発達障害の場合、診断がなくても利用できる公的機関があるようです。たとえば以下のような場所です。
- 発達障害者支援センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 精神保健福祉センター
また、市区町村の保健センターでも、大人の発達障害に関する相談を受け付けている場合があるそうです。
HSPの場合は、カウンセリングを利用するという方法もあります。カウンセラーを選ぶ際には「HSPの傾向がありそうだ」ということを伝えた上で、相談できるかを確認するとよいでしょう。
詳しくは、いろいろ調べてみてくださいね。
うつ病などの二次障害がある場合
自分に合わない環境や周囲の理解不足などにより、二次的に以下のような障害が出ることも。
- うつ病 (気分障害)、軽うつ、不安障害
- 睡眠障害
- ひきこもり、就労の継続が困難 etc.
ちなみに、これらは発達障害やHSPの本来の特性ではないため「二次障害」と呼ばれています。
HSPの人は、その繊細さゆえに「心が疲れ切ってしまう」可能性がありますし、発達障害の場合は、実際にうつ病や不安障害の併発が多いそうです。これはグレーゾーンでも同じことが言えます。
生活への支障や異変を感じたら、早めに心療内科や精神科を受診することをお勧めします。私の経験から、信頼できる先生とそうでない先生がいると感じるので、できれば口コミなどで調べてからの方がいいかも。
グレーゾーンだからこそ‥私なりの実践方法と効果!
私は、おそらく
- HSPはグレーゾーンではなく、
- 発達障害のアスペルガー症候群と
- 発達障害のADHDはグレーゾーン。
しかも軽く「強迫性障害や統合失調症の症状も当てはまるかも」という部分もあります。
20代の頃から、前述のような「具体的な対処法」を取り入れ、独自の対処法を開発したりもしてきました (笑)
ただ、40歳目前での無念な経験をきっかけに「本気で自分をどうにかしたい!」と思い、脳科学や心理学、自己啓発、スピリチュアルなど、あらゆるジャンルの本を読み、とにかく実践!
実践を始めた頃は「気にしすぎだけを改善したい!」と考えていました。ちょっと無理やりな方法を試したことも‥。
でも、実践を重ねるうちに「生きること全般、もっと心がラクで楽しく、幸せになりたい!」と感じました(*^-^*)
だからこそ私の実践は、たとえば「心にいい」と言われる
- 深呼吸や瞑想をすること
- 朝日を浴びること
- 断捨離や整頓、掃除をすること
- 運動を生活に取り入れること
- 自然や観葉植物の力をいただくこと
- 体調や自律神経にも気を使うこと
などを含みます。
自分の感情を受け入れつつ「前向きな考え方を選ぶ」という実践も、無理のない範囲で続けてきました。
また「運気を高める行動」「スピリチュアル」「仏教や儒教などの教え」も、自分がいいと思ったことは取り入れています。たとえば、
- 感謝の習慣をつける
- 愚痴・悪口・不満・文句を言わない
- ネガティブ言葉を使わない
- 自分の「好き」や「楽しい」を大事にする
- 過去や未来でなく「いま」を大切にする
- 笑顔や口角を上げる習慣をつける etc.
本当に無理なく「ゆる~く」という感じで‥(^_^)
最初の頃は愚痴や人の悪口も多かったし、一人反省会もしていたし (笑)
でも少しずつ自分が「よい方向」に変わる感覚があり(進んではまた戻る時もありつつ)、実践から約2年。気づいたら「気にしすぎ」がなくなっていたのです!
- 今まで気になっていたことが「気にならない」
- 一度気にしても「すぐに切り替えられる」
- 気づきはしても「さっと受け流せる」etc.
最後の方は、なんか加速するように自分が変わる感覚がありました☆
不安や超ネガティブも、びっくりするほど少なくなっていたし。
グレーゾーンは複雑で、すべてにおいて「人それぞれ」です。対処法などの合う・合わないも、人それぞれ。
でも、もし私の実践方法に興味のある方や「やってみたい」と思われた方がいらっしゃったら…。このブログを参考に「無理なく」「少しずつ」試してみてくださいね。
まとめ:グレーゾーンは診断名ではないけれど…
「グレーゾーン」とは明確な診断名ではなく、そもそも「あいまいなもの」。
必ず認識や公表をしなければならないものでも、ありません。
強いて言えば、自分で「グレーゾーンかも」と認識することで、生活に役立てることができます!
- 前述のような対処法を取り入れたり
- 自分だけの「トリセツ」や「対処法」をつくったり
- 周りの人に自分の特徴をあらかじめ伝えて理解を得たり‥。
また、グレーゾーンだからこその「よさ」「できること」もあると思うので、お互い極力「いいところ」に目を向けていきませんか? 毎日の自分なりの頑張りを褒め、いろいろなものに感謝もしつつ ‥ (^-^)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。