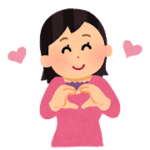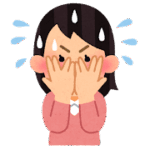よく「昔はこうだった」と話すおじさんがいる。
聞いていて「そうだよね~」と楽しめる時もあれば、「もう、ごちそうさま」って時もある。
でもあれっ? 自分も話してるかも‥「昔はこうだった」って (‘Д’)
自分のためにも、気を付ける方法を考えたくなりました!
ここでは、「昔はこうだった」と話す心理と、聞く側の心理を考え、つい「昔はこうだった」と話してしまいがちな人が気を付ける方法をお伝えします (*^_^*)
つい「昔はこうだった」と話す心理
「AIによる概要」と、私が話す時の心理を考えながら、まとめます。
過去を懐かしんでいる
本当に純粋に。 過去が懐かしい。
「私が高校生の頃はねぇ、まだ携帯じゃなくてポケベルという物があって‥‥」
などと話しているうちに、過去がパ~ッと思い出され、ついつい長く話しちゃう(笑)
現状に不満を感じている
人には恒常性ホルモン (ホメオスタシス) が存在します。
簡単に言うと、私たちは無意識的に「現状を保とうとする」「変化にストレスを感じる」ということ。
(良い方に変化した場合でも、無意識で「ストレス」を感じる)
自分にとって悪い方に変化した場合はストレスも大きく「昔はこうだった」と言いがちに。
たとえば
- 「昔は、若い社員はみんな飲み会に来たものだ」とか
- 「昔は子どもをおんぶしながら家事していたのにね」とか
- 「昔はもっと子どもたちが外で遊んでいた」とか
「現状への不満」というより、「特定の人に対するダメ出し」の場合もある (‘_’)
変化自体がストレスなのに、不満はさらに大きなストレスになるので、それを吐き出して解消したいという心理。この場合、言葉そのものも言い方や表情も「愚痴っぽく」なります (もちろん人や状況にもよります)。
相手に認められたい、自分を認めたい
「承認欲求」が隠れている場合もあります。
- 過去の栄光や、過去に評価されたことを自慢したり
- 「昔すごい経験をした」「若い頃は頑張っていた」などと話したり
- (昔のことなら知識をひけらかせるから) ペラペラ話したり
前述の「現状への不満」とセットの場合もあるし、単純に「自慢話をしたい」みたいなケースもある。
今の自分に満たされていないから話す人もいる。 「昔はこうだった」と話すことで、相手から「すごいですね」と言われたい、自分自身が価値ある存在だと認めて満足したい、という心理です。
ペラペラ話せて気分がいい
昔の話だとペラペラ話せるケースがある。
年齢を重ねるごとに「一年前の出来事はよく覚えていないのに、若い頃の出来事は鮮明に覚えている」みたいなことが出てきました(笑)
もちろん内容にもよるのだけど、昔のことの方が覚えているというか‥‥
といっても、記憶が脳で改ざんされているかもだけど (笑)
いずれにせよ、私の場合「昔はこうだった」という話の方がスムーズにペラペラ話せる時があります。単純に「それが気持ちいい~~」と感じ、つい話してしまうのです (;’∀’)
「昔はこうだった」という話を聞く側の心理
反対に、聞く側の方の心の働きを、考えてみた。
「楽しい」「興味がある」なら聞きたい
たとえ昔の話でも、それが
- つい笑っちゃうほど「楽しい」
- 興味が湧いてきて「おもしろい」
- 自分の好きな分野の話で「ぜひ知りたい」
などの内容なら、むしろ聞きたいでしょう。うざいとは思わない。
また「共感し合える」場合も、基本的に心地いい。たとえば高齢の方同士で「昔はこうでしたねぇ」などと懐かしみながらお互いに気分よくなるのなら、どんどん話した方がよいとも言えるでしょう。
「必要があること」なら聞きたい
たとえば、仕事や何らかの活動などで、昔のことを知っておいた方がいいケースもあります。
たとえば
- 知っておいた方が、自分にとって得な話
- 知っておいた方が、周りの人の役に立てるかもしれない話
- 知らないと自分や周りの人に不利益が被るかもしれない話
などは、ぜひ知りたいでしょう。
どんな時に「うざい」と感じるのか
反対に、相手が昔の話をしていて
- 「うざい」「イライラする」
- 「もう、お腹いっぱい」
- 「そろそろ話題を変えるか退散しようかな」
などと思う時は、どんな時だろう。
- 聞いていても内容がわからず、つまらない
- 聞いていても、興味がわかない
- 相手の自慢や過去の栄光の話で、おもしろくない
- 相手の価値観を押し付けてきて不快
- 全体的に愚痴っぽい話で、気分が悪い etc.
話がすぐに終わるなら、まだいい。ダラダラ長いと飽きたり嫌になったりしてくる。その上「昔はこうだった」という話をしょっちゅうしていると「あの人うざい」になってしまうのかもしれません。
つい「昔はこうだった」と話すことに対し、気を付ける方法
前述を踏まえた上で、気を付ける方法をまとめてみます!
でも気にし過ぎると、誰とも会話できなくなるでしょう (;´・ω・)
つい「昔はこうだった」と話してしまうのもヨシとした上で、ちょこっと気をつけてみる \(^o^)/
その話は相手にとって「必要か」「興味があるか」を考える
「昔はこうだった」とペラペラ話している途中に‥‥
「この話は、相手に必要か」「相手にとって興味があるのか」を、少し考えてみる。
「必要ではない」「興味もなさそう」なのであれば、相手の反応も見ながら、適当なところで話題を変えよう。
それか、うま~く「その話に関連する、相手に必要そうな話題」を交えながら話す (応用編かもしれんけど)。
相手の反応を見ながら話す
そう、相手の反応を見ながら会話する。
人によっては難しいかもしれませんし、逆にHSPのような気質の人は得意かもしれません。
ちょこっとでいい。
相手の表情が「つまらなそう」「嫌そう」なら、昔の話をそろそろやめる。
表情から読み取るのは難しくても、たとえば
- 相手の反応が明らかに薄くなってきた
- 相手の相槌に心がこもっていない (ように感じる)
- 相手がスマホを見始めた
- 相手が貧乏ゆすりや髪を触ったりしている
- 相手が目を合わせなかったり、体が別の方向を向いている
などの場合は「つまらない」と思っている可能性が高いです (もちろん状況にもよりますが)。
「話の長さ」「頻度」を意識する
全ての人が、全ての相手に「おもしろい」「役に立つ」ような話ができるわけではない。
完璧を目指していたら、会話をしたくなくなります (‘_’)
自分も他人も、つい昔の話をしてしまうのはOK!
でも「話の長さ」には気を付けたいと思います。
「昔はこうだった」という話に限らず、自分だけがペラペラ話しているなぁと感じる時は、
- 相手にも質問を投げかけてみる
- キリのいいところで、一度沈黙状態にする (相手の反応や相手がどうするかを見てみて考える)
などをすると、お互いにとって「心地いい会話」になるのかも (でもすべては状況によります)!
もちろん前述の通り、相手の反応を見るのも大事。 相手が「楽しそう」「興味をもって聞いてくれている」「積極的に質問とかもしてくれる」などの場合は、長く話していてもいいかも (でも相手の立場が下の場合は「気を使っている」可能性もある‥)
また「昔の話をする頻度」も大事。
毎日毎日「昔はこうだった」と言っていては、今を生きていないように思えます。自分一人で思い出しているだけなら自由ですが、誰かに聞かせているのなら、その誰かは幸せかなぁ? (でも幸せは心が決めるから、幸せという場合もあるかもね‥)
さらっと前置きをする
「つい」ではなく、「これから昔の話をするぞ」と意識できている場合。
最初に「前置きの言葉」を加えるのも一つ。たとえば
- 「昔の話になってしまうのですが」
- 「まあ、昔と今は違うかもしれないけど」
- 「昔の話を聞いてもつまらないかもだけど」
- 「ごめんね、昔の話をしちゃうけど」etc.
そうすれば相手も「ああ、わかって話しているんだね」と受け入れやすくなる。 自分としても客観的に見ることができ、長々話してしまうことにブレーキをかけられそう (;^ω^)
現状への不満の話は極力やめる
自分の話が
- 昔、自分はできたのに、あなたはできていない
- 昔の自分は頑張ったのに、今の若い人は頑張っていない
- 昔はよかったのに、今はよくない
など「現状への不満」「愚痴」「文句」「人の悪口やダメ出し」などになっていると気づいたら、即やめたい。
言葉そのものだけでなく、おそらく言い方や表情も「よくない」状態になっているでしょう。相手にとって「聞きたくない」「苦痛」なだけでなく、自分の美容や健康にも得はないからです。
まとめ:ああ、本当に気を付けよう
「昔はこうだった」と話す心理と聞く側の心理、つい「昔はこうだった」と話しがちな人が気を付ける方法をお伝えしてきました。
いまいちど、自分も気を付けようと、強く思う (;’∀’)
私の場合、おそらく友人知人だと気を付けられるのだけど、子どもにはペラペラ話してしまう。
特に「私はもっと勉強してた」とか、長々と「昔はこういう物が流行ってねぇ」とか。
たぶん、私が母親から同じような話を聞いたら「また始まった、とりあえず相槌を打っておくか」みたいな気持ちになると思うから(笑)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。