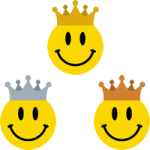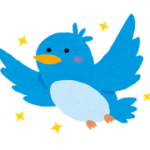高校野球が好きです。 特に甲子園出場校を決める地方大会。
観るための選択肢は「ローカル局の中継」と「球場に行く」のみだったけど‥
昨年から、全国の試合がリアルタイム&アーカイブで観られるようになった (*’▽’)
めっちゃ嬉しくてテンション上がり、今年は観まくっているけど。
あれっ? 意外と「心がラク&幸せ」ではない側面もあるのかも‥‥
ここでは、選択肢が多すぎることのメリットとデメリット、高校野球の配信における具体例、多すぎるものから選ぶ方法、選んだら「これでいい」と思えることも大事、というお話をします。
選択肢が多すぎることのメリットとデメリット
何事にも、いい面&悪い面、あり。
選択肢が多すぎることのメリット
箇条書きで挙げます。
- (内容によっては) ワクワクする
- 自分の好みのものを見つけられる確率が上がる
- 自分にぴたりと合うものを見つけられる確率が上がる
- (選ぶ作業の中で) 自分の興味や関心が明確になるかもしれない
- 自分の可能性を広げられるかもしれない
- 失敗しても、他の選択肢に移行しやすい etc.
好みや合うものは人それぞれ、千差万別。 選んだものが「合わない」「つまらない」とかでも、選択肢が多いほどすぐに次のものを選べ、自分に合うものが見つかりやすくなります。 (もちろん人や状況にもよる)
選択肢が多すぎることのデメリット
主に、以下の3つです。
- 選ぶ際に「考えること」が多くなり、脳が疲れる
- 考えることと共に感情も動くので、心も疲れる
- さまざまなネガティブ感情を抱きやすくなる
3番の「ネガティブ感情」とは、たとえば
- 「いいものを選択しなきゃ」とプレッシャーを感じる
- 選んだ後も「本当にこれでよかったのか」と疑う
- 「やっぱり別のものを選べばよかった」と後悔する etc.
実証もされています。
ジャムの試食販売の調査では「人は選択肢が多いと考えることをやめる (買う気が失せる)」 ことがわかりました。
また、アメリカの心理学者バリー・シュワルツは「選択肢が多ければ多いほど、いいものを選べなくなり不幸を招く」という「選択のパラドックス」を提唱しています。
具体例 (高校野球の試合配信)
昨年・今年と「全国の高校野球の地方大会」が無料でリアルタイム&アーカイブで観られる。
「バーチャル高校野球」というもの。 「ワクワク~♪」「ありがたい!」
反面、以下のようなデメリットも実感&想像できる。
- どの試合を観ようか迷って疲れる
- 選んでも「他の試合の方がおもしろいかも」とか気になる
- どんどん切り替えて他の試合を観るので休憩時間がない
- ずーっと観ていたい、でも家事や仕事をしなきゃでイライラする
- 他のことがおろそかになる
- あっちもこっちも観て睡眠不足になる etc.
もちろん「遠い県の試合も観られる!」とか「感動の試合をリアタイで観られた!」という喜びや感謝もある。でも意外と「脳や心が疲れてぐったり」ということもある (人にもよるだろうけど)。
多すぎるものから選ぶ方法
「AIによる概要」と「私の経験」を掛け合わせてご紹介!
グループ分けする
たとえば
- 食べたいものを選ぶなら「和食・中華・洋食」などに分ける
- 断捨離で処分する物を選ぶなら「衣類・本・文具・キッチン道具」などに分ける
- 着る服を選ぶなら「トップス・ボトムス・アウター」などに分ける etc.
グループに分けると、わかりやすく選びやすくなる。 また「自宅にある衣類が多すぎるから、さらにトップスとボトムスとアウターなどに分けて処分するものを考えよう」など、現状を把握した上で前に進めるケースもあるでしょう。
自分の希望を明確にし、絞り込む
先述と重なる部分もありますが、自分の希望をはっきりさせると選択肢が減る。
たとえば、ファミレスでメニューを選ぶ時は
- 今日は純粋に「食べたいもの」にしよう
- 栄養バランスが整っているものにしたい
- 今は和食の気分
- カロリーが低いものにしよう
- 野菜が多めのものにしたい etc.
でも「一度選んだら、他のものについては考えない」ことも大事かも。たとえば「今日は和食にする」と決めたら「もう洋食と中華のメニューは見ない」みたいな (;’∀’)
自分の生活で優先させることを明確にする
たとえば、ネット上には文章・画像・動画・音楽などがあふれています。
その中から、自分が興味のあるものを見たり聴いたりするのだけど、あれもこれもだと
- 睡眠不足になる
- 食事が味わえない
- 家族や大切な人とかかわる時間がない
- 家事や仕事がテキトーになる
- 勉強や他の趣味ができない
などの可能性も出てくるでしょう (‘_’)
もちろん、それもその人の自由です。
でも、そうなりたくないのなら「生活の中で優先させたいこと」や「優先順位」などを書き出すとよいと思います。優先させたいことを優先した上で「余った時間で、ネットを利用しよう」と思えるといいのかな。
人気のあるものを選ぶ
選択肢が多すぎて選べない。
グループ分けとかしている時間もないし、特に希望もない!
そんな時は、とりあえず「人気のあるもの」を選ぶのも一つです。
- 「人気がある理由がわかる!」と思えるかもしれない
- 「人気があるけど自分には合わないな」と思うかもしれない
- そういう自分の気づきを、会話や発信のネタにできる
などのメリットがあると思います☆
真ん中あたりのものを選ぶ
選択肢が多すぎる時、ひとまず「真ん中あたりのものを選べば無難」というケースもあります。
たとえば
- お寿司 (「特上にぎり」「上にぎり」「並」)
- 教材 (「ハイレベル」「スタンダートレベル」「初心者レベル」)
- 電化製品など (「値段が高い」「中ぐらい」「安い」) etc.
で、特に希望が明確でない場合、人は「真ん中のもの」を選ぶ傾向があるのです。
ここには「損したくない」という心理が隠されているそう。
特に日本人は「真ん中あたりのものを選ぶことが多い」と言われます。 ゆえに真ん中あたりのものを選んでおけば「目立ちにくい」とも言えるでしょう。
誰かに勧められたものを選ぶ
もう、自分では選べない!
周りの人やネットの向こうの人などの「オススメ」を選ぶのも一つです。
ただ「結果的によくないことがあっても、その人のせいにしない」という心でいたい。
「『自分で決めない』と決めたのは自分」なのですから。
考えずに選ぶ
たとえば、多くの選択肢の中から
- 目を閉じてパッと思い浮かんだものを選ぶ
- (見える物の場合) 上を見てからパッと見て視線が止まった所のものにする
- (見える物の場合) 目を閉じて指で全体をなぞった後に指を止め、その止まった所のものにする
少し時間をかけられるなら、くじをつくったり、適当に番号を振ってスマホのくじアプリもいい。
もう「神様が決めてくれた」ことにする!
迷う場合は、どれを選んでも大きな意味で「同じ」なのです。 何を選んでも、そこには「良い面・悪い面」があるし、学びや気づきが得られて成長につながるのでしょう。
選んだら「これでいい」と思えると心ラクハピ
スパッと選べても、熟考して選んでも、迷いながら選んでも‥‥
選んだ後に「後悔」「疑い」「自責」などがあっては、心が苦しい (>_<)
「これでいい」「これがよかったのだ」と思える力があれば、幸せです。
情報や選択肢にあふれる現代は、特にそういう力・スキルが必要となるでしょう。
先述の通り、何を選んだとしても
- そこから学べることがあります。
- メリットもあればデメリットもあります。
- 楽しいこともあれば苦しいこともあるでしょう。
後悔したり自分を責めたりする場合は「きっと、その時の自分の最善の選択。それでよかったのだ」と考えるのも一つ。
また、選んだものにより「失敗した」と思っても、その失敗のおかげで次は気を付けられたり、あるいは失敗の経験が後で思わぬかたちで生きてくる、ということも多いです (*^-^*)
スピリチュアル的にはなりますが「神様や宇宙と呼ばれる大きな存在が、それを選ばせてくれた」「それを選ぶことが生まれる前から決まっていた」という可能性すらあるのかもしれないのです☆
まとめ&調和の光を‥
選択肢が多すぎることのメリット・デメリット・具体例、多すぎるものから選ぶ方法などについて、お伝えしてきました。
近年の夏の猛暑で、夏の高校野球に賛否両論、さまざまな意見が出ています。
多くの意見に「一理あり」という感じで、難しさを感じます。
どの意見にも愛と光を注ぎ、なんとか少しでも調和させられる方法が見つかることを願うばかりです。
関連記事のリンクを貼ってオシマイ。
★選択肢を少なくした方がラクで幸せな理由と、私の実践方法。 | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜
★優柔不断でつらい人へ…心がラクになる考え方や決め方をご提案! | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜
★心がラク! ポジティブな「どうでもいい」の具体例と実感するヒント | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜
最後までお読みいただき、ありがとうございました。