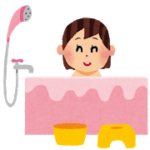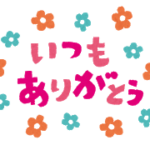当ブログは、生きづらかった私が「ラクで楽しく幸せに生きる」ため、さまざまな実践をしてきた経緯をまとめています。
物心ついた時から20年以上「気にしすぎ」「不安が多い」「超ネガティブ」‥(*´Д`)
おそらく「HSP (超敏感体質)」と「発達障害」の特性をあわせ持っています。
でも発達障害の方は、自己診断してもチェック項目に「全く当てはまらない」ものもあるし、程度の軽いものもある。いわゆる「グレーゾーン」だと思うのですが、それらの傾向があるのは確か。
発達障害は「脳の機能」によるので、私に当てはまる特性が全くなくなったわけではありません。
自他共に認める「ちょっと変な人」であることは変わらない、どころか変さは増したかも(笑)
でも今は「生きづらさ」を感じておらず、ラクで幸せなので、自分の中では「HSPだろうと発達障害だろうと、もうどうでもいいや」って気もしています‥ ( ;∀;)
この記事では「発達障害」について、いくつかの具体例と共に解説 (‘ω’) 後半にチェックリストもつけますよ!
発達障害とはズバリ!
発達障害は「脳の機能」によるもの。
脳の発達 (成長の進み方) に早い部分・遅い部分があり、脳の機能にデコボコが生まれることで起きます。
たとえば、
- 得意なことと不得意なことの差が激しかったり
- 強くこだわる部分と全くこだわらない部分が極端だったり
- 敏感なことと鈍感なことの差が激しかったり‥‥。
自分の努力が足りないわけではない。むしろ真面目だったり表裏のない性格だったりする人が多いのですが、結果が伴わないため「努力が足りない」「怠けている」などと言われることがあります。
このような結果、
- 「周りに理解してもらえない」
- 「自分って変なのだろうか」
- 「生きづらい」 etc.
と感じ、うつ病などの心の病まで抱えるケースもあります。
原因については「遺伝や環境」と示す、いくつかの研究結果があります。親子で同じような「アンバランス」が見られることも実際に多いのですが、まだ確実であるとは言えません。
他にも、原因については「子どもの頃の病気」「生活習慣」など、いろいろ言われてはいますが、すべて「そうかもしれない」だけで確実なことは不明。
ちなみに「発達障害」という言葉や概念の歴史は、意外と浅いです。日本では「片づけられない女たち (サリ・ソルデン著) が訳された2000年頃から、少しずつ認識されてきたようです。
発達障害には種類がある
「発達障害」は、さらに3~5種類に分類されますが、複数の障害や特徴が組み合わさっている人も珍しくありません。
また同じ診断名でも「表面に現れる特徴」としては正反対になるケースもあり、診断が難しいともいえます。(特徴が正反対でも「社会に適応しにくいこと」は共通)
程度の差もそれぞれ。生活に大きな支障を及ぼすケースもあれば、周りの人には一見わからないようなグレーゾーンのケースもあり、個人差が大きいです。
ここでは、実際に私が接してきた発達障害の方やグレーゾーンの方を参考に、具体的な特徴や例も交えながらご紹介していきます。
広汎性発達障害
広汎性発達障害は、コミュニケーション能力や社会性 (人とのかかわり) に関する脳の機能の障害。主なものに「自閉症スペクトラム」と「アスペルガー症候群」があります。
自閉症 (自閉症スペクトラム)
自閉症の特徴として、以下のようなことが挙げられます。
- 興味・関心が狭い範囲に限られやすい
- コミュニケーションが上手くとれない
- 感覚がとても敏感だったり、逆にすごく鈍感だったりする
- パターン化した行動・こだわりを持つ
- 独特な行動や振る舞いがある
たとえば、こんな例があります。
- 鉄道に関する知識は専門家のようだが、他のことには一切関心がない
- 伝えたいことが言葉にまとめられず、上手く伝えられないことが多い
- 光や特定の音、手触りなど、極度に怖いものや嫌なものがある
- 急な予定変更や想定外の出来事があるとパニックになる
- ドアの手前で必ず体を揺らしてから開けるなど、独自の決まった動きがある
アスペルガー症候群
アスペルガー症候群は、広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプです。 やはり
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、興味・関心の偏り
を持つと言われています。
ただ、自閉症 (自閉症スペクトラム) との違いとしては、幼児期の言葉の発達の遅れがないこと。よって周りから見て「障害があること」がわかりにくいと言えます。
成長と共に、たとえば
- 集団やグループでの活動が極度に苦手
- 相手の顔を見ても、その人が考えていることや感じていることがわからない
- 他の人とは違う「自己流」のことが多い
- すごく得意なこととすごく苦手なことの差が激しい
- どうやら空気が読めない行動や失礼な発言が多いらしい
ことなどに気づき、「アスペルガー症候群かも」と自分や周りが思うケースが多いです。
注意欠陥多動性障害 (AD/HD)
注意欠陥多動性障害(AD/HD)の特徴として、以下のようなことが挙げられます。
- 集中することが難しい(不注意)
- じっとしていられない(多動・多弁)
- 考えるよりも先に動く(衝動的に行動)
たとえば、こんな例があります。
- 困っていそうな人にはすぐに気づくが、他人の髪型の変化などには鈍感
- 試験中や大切な会議中なのに気が散ったり、きょろきょろしたりすることが多い
- 予定や持ち物などを「つい忘れる」ことが頻繁にある
- 仕事や私生活の中で「ウッカリミス」が多い
- 優先順位をつけて作業や行動をすることが難しい
- 立っている時に手足を動かしたり、座っている時に体を揺らしたりする
学習障害(LD)
学習障害(LD)とは、全般的な知的発達に遅れはないにもかかわらず、特定の能力を学んだり行なったりすることが難しい状態のことを言います。
これは単に「国語が苦手」「数学が苦手」ということではありません。具体例としては、
- 読解力 (文章を読んで意味を理解する力) だけが極度に不足している
- 文字・単語・文章を正確に読めなかったり、読むのが極端に遅かったりする
- メモにとっている時「書くこと」だけに必死で、内容が全くわからなくなる
- お釣りの計算 (簡単な暗算) や金銭管理が極端に苦手だと感じる
- 1Kg=1000gなどの単位換算が覚えられなかったり意味が分からなかったりする
- 九九を覚えてはいるが、生活の中で上手く使えない
などが挙げられます。
他にもある「発達障害」
上記の他にも、政府広報オンラインによると、
- トゥレット症候群‥特徴的な体の動きや発声を無意識に行う
- 吃音(症)‥一般的に「どもる」と言われる話し方になる
が紹介されています。他にも、
- DCD (発達性協調運動障害)‥体の動かし方や手先が不器用だったり不自然だったりする
- APD (聴覚情報処理障害)‥聴覚に問題はないが、話を聞き取る力が極端に不足する
などがあるようです。興味のある方は書籍やインターネットで調べてみてくださいね。
発達障害の特徴をチェック
前述の通り「発達障害」といっても種類があります。ネット上では、発達障害の種類別のセルフチェックリストも、いくつか探せますね。
ただ、この記事では浜松医科大学名誉教授・高田明和先生の著書「HSPと発達障害」を参考に、「発達障害でよく見られる特徴(症状)」を載せさせていただきます。
これは、医療機関の正式な診断基準 (米国精神医学会によって1994年に作成されたDSM-Ⅳ) に基づいたものだそうです。
全部で30項目ありますが、程度の差はあれど「誰にでもあること」が多いと思うでしょう。もし、ご自身でチェックする場合は、
- あまりに落差が激しいのか
- それにより日常生活に支障が起きているか
を意識しするとよいそうですよ。
【発達障害度チェック】 ~参考文献「HSPと発達障害(廣済堂出版・高田明和著)」~
- 人が何を話しているのかわからないことがある。
- 一つのことに興味を持つと、そのことが頭を離れない。
- 一方的に自分のことばかり話すことがよくある。
- 自分なりの儀式を持ち、それをやらないと不安になる。
- 思ったことをすぐ口に出し、後悔したことがある。
- 長い時間待つことができず、途中で帰ったり順番を無視したりしたことがある。
- 物事を先延ばしにする傾向がある。
- 退屈に我慢できない。
- 部屋が片付けられず、一緒に住む人とよく揉める。
- 買い物がやめられない。
- 料理の段取りが苦手で、つくりながら洗うなど二つのことが同時にできない。
- ストレスを感じると、身体のどこかを動かさずにはいられない。
- 特定の食べ物しか口にしない。偏食が強い。
- 皆が笑っていることが面白く思えないことが多い(微妙な感情の欠如)。
- 頭の中に次々といろいろな考えが浮かんできて不安になる。
- タバコやアルコールをどうしても手放せない(依存)。
- 目新しいものに、すぐに飛びつく(新奇追求傾向)。
- 昼間でも眠くなることがある(睡眠障害)。人よりも長く寝る。
- 感情の起伏が激しいと言われる。
- 得意なことと不得意なことの差が激しい。
- 心配事が頭に浮かぶと、どんどん大きくなり不安や恐怖に陥る。
- 人と離れた時や仕事の帰り道などで、いきなり気分が変わることがよくある。
- 「他の人が考えもつかないことを考える」と言われたことがある(創造性)。
- 学歴や育ちに関係なく「自分はダメだ」と感じることがある(自己肯定感の低さ)。
- 他の人が気づかない音や細部が気になることがある。
- 小説や映画で、ストーリーがよく理解できないことがある。
- 電話が苦手で、出るのが怖くなることがある。
- 同じことを何度も繰り返す傾向がある。
- 仕事の期限が守れないことがある。
- 職場でコピー取りや掃除などの雑事が苦手で「気が利かない」と言われる。
このチェックリストも、ネット上の他のチェックリストもそうですが、飽くまで簡易チェックです。実際の診断は医療機関でのみ可能です。
大人で「発達障害の疑いが強い」「生活に非常に困難を生じる」という方は、医療機関 (心療内科や精神科) を受診することをお勧めします。
なお、他の障害や症状も併せ持っていたりすると、医師でも判断が難しい場合もあるようです。
完全に「発達障害」と診断された場合は、自己流の方法や私のサイトで紹介しているような方法の実践は控え、医療機関による治療や専門家 (医師・カウンセラーなど) のカウンセリング・指導・トレーニングなどを受けるとよいとのことです。
まとめ:境界線上の人も増えている
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
「発達障害」というと、その名前からも「悪いイメージ」を抱く方が多いと思います。
しかし最近は、有名人で「自分が発達障害であること」を明かす人が続々出てきていますし、アインシュタインやモーツァルト、ゴッホなども発達障害だったと言われています。
二次障害として心の病を発症する人も多いですが、特性を生かしている人や「人と違うのがいいのだ」と前向きな人もいます!
発達障害の種類や程度にかかわらず「自己肯定感が高いか低いか」が影響するとも言えるでしょう。
発達障害もHSPもそうですが「明確な診断は下されないけど、そのような特徴や症状に苦しむ」、いわゆる「グレーゾーン」の人も増えてきています。
以下の記事では「グレーゾーン」について、まとめました!
私、HSP&発達障害かも【No.3:グレーゾーンだからこそ‥】 | 気にしない自分をつくろう!〜ラク楽イキ生きブログ〜 (kinisinai-jibun.com)
長い文章にお付き合いいただき、感謝いたします‥m(__)m。